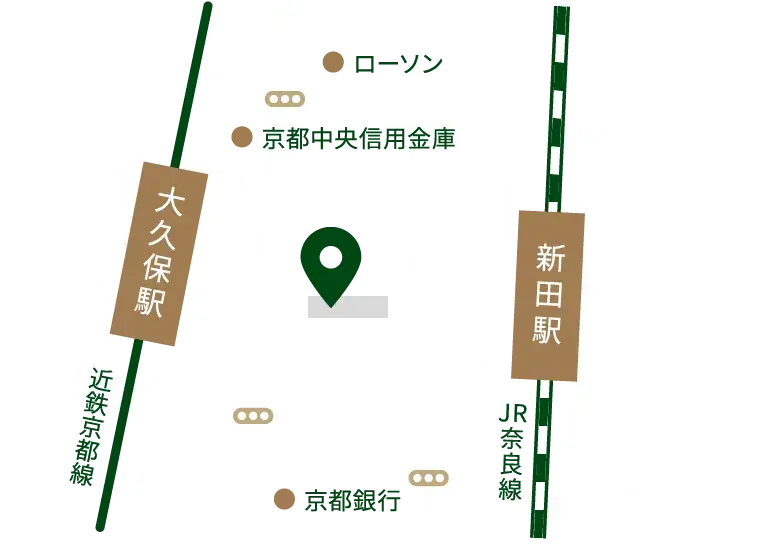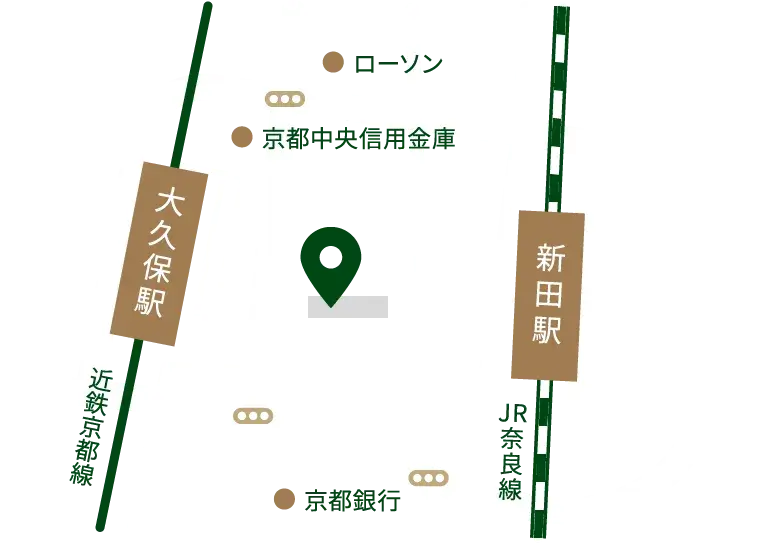口腔機能低下症について
こんにちは。やまもと歯科大久保院です。今回は口腔機能低下症についてお話ししていきます。 そもそも口腔機能低下症というのは、どんなものなのか、どんな症状が出るのかわからない方は多いですよね。そこで、いったいどんな症状があるのかお伝えしていきます。 口腔機能低下症の代表例 咀嚼機能低下噛む力が弱くなってきた、硬いものが食べにくくなった。 口腔不潔口の中が汚れている、舌の汚れ。 舌口唇運動機能低下舌や唇の動き、滑舌が悪くなった、食べこぼしをするようになった。 口腔乾燥お口の中の水分量が不足するようになった。 伵合力低下噛む力や残っている歯の本数、食べ物が口に残るようになった。 低舌圧舌の力が弱くなっている。 意外と身近で、よくある症状のようにも感じられるかもしれません。これら3項目以上に該当する場合は、口腔機能低下症と診断され、歯科医院での対応が必要となります。 口腔機能低下症を予防するためには、日常的な口腔ケアと健康的な生活習慣が大切になってきます。そこで、どのような予防方法かご紹介します。 口腔機能低下症の予防方法について ①バランスの良い食事 様々な食品をバランスよく摂取 干し芋など繊維質の多いものや、硬いものを積極的に取り入れる ②十分な水分を摂る 1日のうちに1.5~2リットルの水分を摂取 こまめに水分補給をしてお口の中を潤す お口をよく動かすようにする 唾液腺マッサージを1日3回する ③適切な歯磨き 1日3回、毎食後に歯磨きをする 歯間ブラシ・フロスを1日1回以上は使う フッ素入りの歯磨き粉を使う ブクブクうがいをしっかりする 入れ歯の汚れをしっかりとる ④定期的な歯科検診 最低でも年に1~2回は歯科医院に受診 虫歯や歯周病の早期発見・治療 ⑤口腔体操の実施 舌や頬、唇の運動を定期的にする 「あいうべ体操」などの習慣化 ⑥禁煙 喫煙は口腔内環境を悪化させるため、禁煙を心がける ⑦ストレスの管理 過度のストレスは唾液分泌に影響を与えるため、適切なストレス管理をする これら7つの予防方法を日常生活に取り入れることで、口腔機能の維持と向上が期待できます。 まとめ 日常生活への影響が小さいため、本人の自覚がないまま進行しやすい傾向にあるため、早期発見と早期対処が重要となります。小さなことでも疑問に思ったり何かご相談があればお気軽にお問合せください。全身の健康のためにもお口の機能を保ちましょう。
2026.01.07